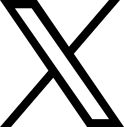2025年第3回定例会 本会議一般質問を行いました

9月12日、本会議一般質問を行いました。通告は以下の通りで、その他として「中野駅前大盆踊り大会について」質問をしました。本文は以下の通りです。今後、答弁も分かり次第、追記したいと思います。
1.次期中野区基本計画の考え方について
2.中野駅新北口駅前エリア再整備事業について
3.気候危機対策について
4.感染症対策について
5.保育施策について
6.鷺宮地域のまちづくりについて
7.その他(中野駅前大盆踊り大会について)
2025年第3回定例会にあたり、日本共産党議員団を代表して一般質問を行います。
1.次期中野区基本計画の考え方について
はじめに、次期中野区基本計画について伺います。現在、来年度から計画年度が始まる中野区基本計画の策定作業が行われています。子育て先進区をはじめ、区政のさらなる発展のために、より良い中身となるよう、私自身力を尽くしたいと思います。
基本計画は基本構想にある中野区が10年後に実現を目指す街の姿を実現するための施策となっています。計画の5ページ、「計画の進行管理」では、「目標と成果による区政運営を進めます」として、「定期的に目標と現状について検証や評価を行い」と書かれています。区は4月24日に総務委員会において、「中野区基本計画の進捗状況について」という報告をおこなっていますが、ここからはそれぞれの政策・施策の進捗状況しか分からず、そのため6月に総務委員会に報告された「中野区基本計画(骨子)について」において、それぞれの施策がなぜ統合されたのか、成果指標は妥当なのかなど、基本計画を進める上での区の評価が分かりません。これでは、区政運営の柱であるべき基本計画がこれまでの結果を次期に生かすことができなくなるのではないでしょうか。
Q1.中野区基本計画の策定にあたって、現計画の進捗の評価を区として明らかにすべきではないでしょうか。
A.
6月に報告された基本計画(骨子)では、策定の背景として、「ライフスタイルの変化と孤独・孤立」の中で、「一人で生きていく」ことなど、多様な生き方・ライフプランの存在が想定されていないのではないかと感じました。確かに、支援を必要とする人が確実に支援を受けられることは必要ですが、この数年で大きく変わったのは、従来の家族観や性別役割分業のあり方にとらわれず、「自分らしく生きていく」というジェンダー平等の考えが広がったことではないでしょうか。
Q2.中野区はこの点について、どのような認識でしょうか。また、ジェンダー平等の視点を次期基本計画に取り入れ、シングルの支援を含め多様な生き方を支える施策展開が必要ではないでしょうか。
A.
重点プロジェクトについて言うと、骨子には「気候危機」どころか、「気候変動」という文言すら入っていません。区は区政運営の基本方針には入れる考えのようですが、気候危機対策は、直接的な二酸化炭素排出量の削減政策から、熱中症などから区民を守るソフト・ハード両面での適応策、施設などの仕様や区民の意識醸成など、部署をまたがる総合的な取り組みが必要とされており、まさに重点プロジェクトに必要な考えです。昨年策定された脱炭素ロードマップにおいても、分野ごとの施策と取組みを掲げ、そうした考えを示しています。現行の基本計画では、「活力ある持続可能なまちの実現」の中に、「脱炭素社会の実現を見すえたまちづくりを展開します」と一項目に収まっています。しかし、気候危機の事態の切迫性・重大性を鑑みれば、「気候危機対策をどのように展開していくか」ということを前提にまちづくりなども考えていくべきです。
Q3.重点プロジェクトに「気候危機」の文言を入れることとともに、プロジェクト3のあり方を、「気候危機対策」を前面に据えたものにすべきと考えますが、いかがでしょうか。
A.
わが会派ではこの間、生活再建型債権管理を区政に取り入れるよう求めてきました。第1回定例会の予算特別委員会において、「総合的な相談を受け持つ福祉総合相談部門の設置」を提案したところ、「令和8年度以降の組織を検討する中で福祉に関する相談の在り方についても検討していきたい」と答弁されています。
Q4.その後の検討状況がどのようになっているのか伺います。
A.
差別・排外主義を許さない区の姿勢について伺います。中野区は2022年に人権及び多様性を尊重するまちづくり条例を制定しました。第2条では、「全ての人が、性別、性自認、性的指向、国籍、人種、民族、文化、年齢、世代、障害その他これらの複合的な要因による差別を受けることなく、それぞれの能力を発揮し、地域社会の一員として暮らすことができることを基本理念とする」と述べています。様々な方が暮らしている中野区がこのような条例を制定したことは区の姿勢を示すものとして極めて重要であると考えます。
しかし近年、特に外国人に対する排他的な主張を掲げる人々が散見されます。「外国人の就労が賃金引き下げ圧力となっている」、「日本の健康保険制度を利用するために、外国人が流入してきている」など、デマや印象操作などで、外国人に対する嫌悪感情を煽る許しがたいものです。
区は骨子の中の「政策1・施策2多文化共生のまちづくりの推進」において、外国人住民等が地域で安心して暮らすことができる施策の展開を考えていますが、その中身は「生活に必要な環境を整える」という中身になっています。外国人に対する差別感情が広がることは、ともに中野のまちを作る上で大きな問題になると考えます。
Q5.区として、「差別・排外主義は許さない」という姿勢を表明するとともに、施策展開を考えるべきではないでしょうか。見解を求めます。
A.
2.中野駅新北口駅前エリア再整備事業について
続いて、中野駅新北口駅前エリア再整備事業について伺います。
中野区は今後、民間企業に対してこの地区の再開発について事業採算性などを聞くサウンディング型市場調査を行うとしています。区は「まずはサウンディング調査で評価を聞き、その後区として必要な事業計画の修正を行う」という立場ですが、それでは今回ストップした計画の時に、容積率の割り増し、用途構成の見直し、などが幾度も発生したように、事業者に言われるがままに計画の修正を受け入れることにもつながりかねません。
Q1.まず、このまちづくりで区が何をしたいのか、譲れないものは何か、という考えを示すことが必要ではないでしょうか。見解を求めます。
A.
区長は第2回定例会冒頭の行政報告において、中野サンプラザまちづくりについて、野村不動産との協定解除に至った理由を述べたくだりで、「何より私が残念に感じたのが、子どもの遊び場や、屋上広場、展望施設の規模など区民が直接利用する施設の魅力が認可申請時に区が同意した事業計画と比較して低下している」と述べていました。
Q2.区は修正する事業計画において、「子育て施設」について、どのようなものを考えているのでしょうか。お答えください。
A.
中野区が昨年度に策定した脱炭素ロードマップでは、「中野駅周辺まちづくりにおける対策促進」において、「建築物のゼロエミッション化を促進します」などと取組が述べられています。
Q3.この計画の修正にあたってはこの方針に則ったものすべきと考えますが、いかがでしょうか。
A.
7月に行われた中野駅新北口駅前エリアにおけるまちづくりについてのワークショップを見学させていただきました。そこで出された意見を伺うと、「緑がある憩いの場所」や「ベンチを設置して歩きやすい空間」など、新しい視点がたくさん寄せられていました。先日開催された区議会の委員会で「そうした意見をどう受け止めているか」と尋ねたところ、緑ある空間が大事だと思う旨の答弁がありました。先ほど触れた脱炭素ロードマップにも「二酸化炭素吸収・緑陰形成につながる緑化」が述べられています。
Q4.こうした意見を計画の修正に取り入れるべきと考えますが、見解をお答えください。
A.
中野サンプラザを改修しての利活用に関連して伺います。区はこれまで中野サンプラザを大規模改修した場合、100億円、先日の区長記者会見では170億円が必要となり、事業採算の観点から難しいことを述べてきました。確かに、区の従前資産を活用する場合と異なり、誰が莫大な改修費を負担することになるのかなど、実現には多くの課題があることは承知しています。同時に、一定の声があることも事実です。そうした区民の方々と新たなまちづくりを考える上でも、丁寧な情報提供をすべきです。
Q5.その点から、今後実施するサウンディング型市場調査において、利活用が可能かどうか聞き取りを行ってはどうでしょうか。
3.気候危機対策について
続いて、気候危機対策について伺います。気象庁は先日、今年の夏は平年に比べ2.36度気温が上昇し、観測史上最高を記録する「異常な高温」だったと発表しました。年々上がり続ける気温は文字通り私たちの生存を脅かしています。世界では気温上昇を1.5度未満に抑えようと目標が提起されていますが、現実の取り組みはそれには遠く及ばず、世界の二酸化炭素削減目標を達成したとしても3度上昇が見込まれており、1.5度目標の達成は極めて厳しい状況です。また、そうした中で日本が果たすべき役割は大きいものがあるにもかかわらず、政府はG7で唯一石炭火力発電からの撤退期限を示さない、再生可能エネルギー導入目標も極めて低い、二酸化炭素排出量の削減目標も1.5度目標に整合しない姿勢のままです。そうした情勢の中で区は次期環境基本計画を策定することになります。
Q1.中野区として1.5度目標の達成が危ぶまれている現状についてどのように認識しているのでしょうか。またそうした中で、どのような二酸化炭素の排出削減目標を掲げるつもりでしょうか。お答えください。
A.
民生部門からの二酸化炭素排出量が多い中野区にとって電力からの二酸化炭素排出量を削減することが重要であることは度々指摘してきました。そうした中、中野区が太陽光発電設備設置助成を実施していることは重要です。しかし、全体の世帯数から見れば、電力を再生可能エネルギーに切り替えた世帯はまだ多くはないのではないでしょうか。その原因の一つには、初期費用の問題もあると思います。区は再生可能エネルギーへの転換を阻む様々な障害を取り除いてほしいと思います。江戸川区は来年1月に事業者と地域エネルギー会社を設立することを発表しました。この会社は、太陽光パネルを既存の戸建て住宅に無償で設置をし、パネルは会社が所有、住宅側は安価な電気使用料を会社に払うという枠組みです。
Q2.こうした例にみられるような、再生可能エネルギーへの転換を進める施策を展開していくべきではないでしょうか。
A.
二酸化炭素排出量を削減する取り組みとともに、区内のエネルギー消費量を減らす取り組みも重要です。今年の夏の暑さはもちろん異常気象によるところが大きいですが、東京で進行するヒートアイランド現象の影響も見逃せません。都市が発生させる膨大な熱が東京を温めています。
中野区は2023年に脱炭素社会の実現に向けた区有施設整備方針を策定。これにより、今後の新築・改築においては、ZEB ReadyもしくはZEB Orientedとするとともに、改修時に高断熱・高効率の設備の導入が謳われていますが、それでは多数の施設が改善されないまま長い間残ることになります。
Q3.そのために、断熱化などのエネルギー消費量を減らす独自の取り組みを行うべきと考えます。
A.
中野区の緑化の指標として、みどり率が使われています。それを見ると、区内の緑は減少していないように見えます。しかし樹冠被覆率という樹木がどれだけ地面を覆っているのかという指標で見ると、中野区ではこの間大きく緑が減っていることが分かります。それだけに区は積極的に木陰を増やす政策を取るべきではないでしょうか。8月に環境審議会から出された次期環境基本計画に盛り込むべき事項についての答申には、緑被率・みどり率とともに、樹冠被覆率を向上させる取り組みを求めています。そして、「樹冠被覆率についての調査実施や指標設定についても検討すること」を求めています。
Q4.次期環境基本計画では、樹幹被覆率を指標として導入すべきではないでしょうか。
A.
計画の進行管理について伺います。気候危機に対する取り組みは「緩和策」「適応策」ともに様々な部署にまたがるものです。それだけに環境部が他部署の施策の進行管理についても責任をもって取り組む必要があります。
Q5.区として、環境基本計画の進行管理のためにどのような体制を組んでいくつもりなのでしょうか。
4.感染症対策について
続いて感染症対策について伺います。今年の夏は新型コロナウイルスの感染が爆発的に広がりました。ニンバスとも呼ばれる新たな変異株は、これまでの免疫をすり抜けて感染することもあり、新型コロナ対策の難しさを物語っています。新型コロナは定点調査になり、その拠点数も減り、感染者数の報道もほとんどされなくなり、あとかも「コロナもうない」とも言わんばかりの状況になっています。
そうした中で、5類化以降、対策も自己責任化されています。しかし、そのことについて十分な周知が行われているとは言い難い状況です。
中野区ホームページではマスク着用について、咳エチケットの項目の中に、「咳のある時はマスクをする習慣」として載っているのみで、独立した対策として掲げられていません。無症状者も感染を広げるからこそ新型コロナの対策が難しい理由であり、今回のような感染拡大期にマスク着用者が多ければ、大きな効果を発揮したはずです。
Q1.区は感染症予防におけるマスク着用についてどのような効果を認めているのでしょうか。また、ホームページ上でも適切な周知を図っていくべきではないでしょうか。お答えください。
A.
区のSNSであるX上での発信では感染拡大への警戒を呼び掛ける発信は全くありません。法的に求められているからとのことですが、この夏はほぼ毎日、「熱中症警戒アラート発表中」と呼びかけていました。こうした発信があることで、適切な熱中症対策を意識するきっかけになったと思います。
Q2.例えば、感染拡大期に感染症発生動向調査週報へのリンクを張り、警戒と対策を呼び掛けるなど、感染症の拡大を防ぐための適時適切な発信を検討すべきではないでしょうか。
A.
災害時に感染症が蔓延した場合、さらなる医療機関のひっ迫を招くと同時に、普段なら救える命も救えないという事態にもなりかねません。大勢の被災者が避難する避難所での感染拡大は絶対に防がなければなりません。
Q3.避難所における感染症対策の重要性について、区の認識を伺います。
A.
避難所における感染症拡大を防ぐためには、空気清浄機は効果があります。現在、避難所に指定されている学校には、数台の空気清浄機があり、体調不良の方がいる教室などには設置するつもりのようです。しかし、感染拡大を防ぐためには、さらなる配備が必要ではないでしょうか。
一般財団法人「住宅都市工学研究所」は石川県輪島市と災害時に空気清浄機を優先的に供給する協定を結びました。
Q4.中野区でもこうした協定を結び、避難所への空気清浄機のさらなる配備を検討してはいかがでしょうか。
5.保育施策について
続いて保育施策について伺います。この数年、認可保育園では定員割れが続き、経営に深刻な影響を及ぼしています。区は収入に対する影響額の割合が少ないとして、減収補填を実施していませんが、23区ではすでに16区が実施しています。私立保育園園長会の毎年の予算要望でも掲げられています。園長会からは、「減収補填が認められないならば、せめて定員変更の許可を出して、職員の必要人数が減らせるようにしてほしい」との要望が出されています。区が待機児童対策として、設置を進めておきながら、定員割れという新たな事態に対応策を出さないことは無責任です。
Q1.改めて、減収補填制度を実施すべきではないでしょうか。答弁を求めます。
A.
パート加算単価の引き上げについて伺います。パートで働く多くの方々が保育園の運営を支えていますが、賃金は低く抑えられています。その原因として、パート加算単価の改善が長年図られていないことがあります。区内のある保育園ではパート募集の賃金が2006年度は時給850円、2024年度は1165円と1.37倍になっているにもかかわらず、中野区のパート加算単価は2006年度から月10万4600円と変わっていません。これでは処遇の改善は困難です。
Q2.区はパート加算単価の引き上げを行う必要があるのでしょうか。お答えください。
A.
こども誰でも通園制度の議論の際、わが会派は保育の必要性の要件見直して希望するすべての子どもたちに質の確保された保育を保障すべきであること、保育士の処遇改善と配置基準の抜本的改善を行い、公的保育を拡充することで「誰でも通園」の土台をつくることを求めました。
2024年度から、3,4,5歳児の保育士の配置基準が見直されましたが、期間の定めのない経過措置となっています。多くの保育園ではこの見直された基準でも児童の数が多すぎるとして職員を配置しており、負担になっています。
Q3.質の高い保育を実施できるよう、職員配置基準を引き上げるための独自の加算を実施すべきではないでしょうか。
A.
4月26日、「区内で震度5強以上を記録する地震が発生し、子どもたちを確実・安全に帰宅させる必要が生じた場合」を想定して、中野区立小・中学校・幼稚園合同引き渡し訓練が行われ、非常に意義があったと聞いています。しかし、私立保育園の方からは園長会でこの訓練の存在を知り、「ぜひ参加したかった」との声も聞いています。きょうだいで保育園や幼稚園、小中学校に同時に通う子どもたちは多くいます。
Q4.来年度の引き渡し訓練の際には、事前に内容をお知らせし、保育園や幼稚園に参加を募ってはいかがかでしょうか。
6.鷺宮地域のまちづくりについて
続いて鷺宮地域のまちづくりについて伺います。妙正寺川をはさんだ白鷺2,3丁目にまたがる鷺宮西住宅では、調節池の整備などと合わせた建て替え事業の準備が進んでいます。そうした中で団地にお住まいの方々からは、「建て替えた後に戻り入居ができるのか」、「定期借家だが、建替えの延期により長年住むことになったため、建替え後も住み続けたい」などの要望が出されています。現在示されている住戸の計画では、4棟を敷地いっぱいに建てるものとなっており、相当の建設期間が想定されます。そうなれば、散り散りになった居住者の方が、孤独化することにもつながりかねません。戻り入居のための棟を別に建てることも考えるべきです。
Q1.中野区としてこうした「住み慣れた地域に住み続けたい」という区民の要望を受け止め、公社に対して意見を伝えていくべきではないでしょうか。
A.
鷺宮地域で課題となっている西武新宿線の踏切渋滞解消に関連して、横浜市の相模鉄道鶴ヶ峰駅付近連続立体交差事業が複線シールドでの地下化を実施していることを以前紹介しました。7月に発行された「鶴ヶ峰連立NEWS 第11号」では、来年度にシールドマシンによる掘削を開始すると発表がありました。この事業は、2022年1月に都市計画決定され、現在計画通りに進行し、2033年度に完成予定となっています。横浜市にも問い合わせましたが、事業に伴う立ち退きはほとんどなかったそうです。複線シールドでの地下化の優位性が事実をもって証明されていると感じます。
中野区は、中井‐野方駅間の単線シールドでの地下化が立ち退きなどで大幅な事業期間延長に直面していながら、複線シールドでの地下化を全く検討するつもりがありません。踏切渋滞の早期解消を本当に実行するつもりがあるのでしょうか。
Q2.野方以西の複線シールドでの地下化を区として検証することや、東京都に検討するよう求めることなどをすべきと考えますが、見解をお答えください。
7.その他
最後にその他として中野駅前大盆踊り大会について伺います。8月2,3日に行われた同イベントには区内外から多くの方が訪れたと聞いています。しかし開催後、区民の方SNSへの投稿で、8月1日の「ピンク盆踊り」と題した前夜祭イベントにおいて、四季の森公園内にアダルトビデオ撮影用の車が配置され、記念撮影なども行われていたことを目にしました。区の公園で衆目に晒される形で、こうしたことが行われたことに憤りを覚えます。
区に問い合わせたところ、イベントの内容については告知されておらず、その後、区は「事前にこのような内容が含まれていることを分かっていれば使用許可を出すことはありませんでした」と抗議文を出しています。
実行委員会は8月28日、声明を出しましたが、その中身は、事前の申請に不備があったことでご迷惑をおかけしたとお詫びするもので、再発防止として何をするのかも全く分かりません。来年以降、どのように対策を取るつもりなのか見えず、区民の一人として不安を覚えます。
Q1.区はこの8月1日の「ピンク盆踊り」について、どのような点が不適切であると考えているのでしょうか。
A.
Q2.また、再発防止として区は何を考えているのでしょうか。誓約書の提出といったやり方も検討すべきではないでしょうか。
A.
合わせて答弁を求め、私のすべての質問といたします。